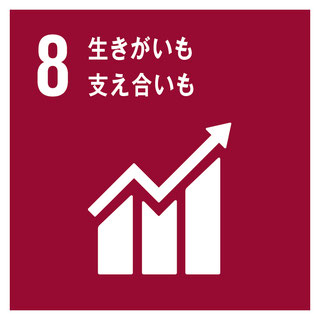SDGsとはSustainable Development Goals(持続可能な開発目標)のことです。
むずかしい話は抜きにして、目標を持続・継続しなければお話にならないということです。
「開発目標」の開発ってなに?「2030アジェンダ」って?とわかりづらさは枚挙にいとまがありません。
そこで提案です。
町区内の問題として、より身近に感じるために「開発」を「解決」という言葉にすり替えてみたらいかがでしょうか。
互近助防災のページでもお伝えしましたが、公助の限界が大災害の度に白日に晒されています。
まずは、身近な問題解決のために「自助力×近助力」を共有し育てることです。
そうすることで、共助・公助とは何なのかを考えるきっかけができるのです。
そこで、町区のみなさんが日常で実践できる持続可能な14開発(解決)目標をピックアップしました。
あなたができる解決目標はいくつありますか。
すぐに行動できることはありますか?
遠くのSDGsより近くのSDGsから…はじめる
ご紹介していいるのは本家のSDGsではないので、2030年までという期限はありません。
なりちょSDGsは無期限です。
「誰もが住み続けられるまちづくりを」を掲げるNPO法人の自助サポートセンターが推奨している
「町内会を変えるための17の目標」の中から、稲荷町にふさわしいと思われる目標をピックアップしました。
町区民が安心して生活できる町づくり
- 安否確認システムを利用した防犯、防災の正しい知識の広報活動
- ながら防犯サポーター制度(令和4年度より活動)の実施で町内見守り
- 従来の自主防災組織だけでなく互近助防災の実現
- 地元警察との連携
生きがいを感じてもらえる町づくり
- 集落センター等の施設を利用した子育て世帯へのお手伝い
- 60歳代~80歳代の元気な住民による「ろっぱ倶楽部(令和4年度より活動)」で地域活性化
- ミニデイサービス・おしゃべり広場などのイベント
住み続けられるまちづくり
- 安心・安全なまちづくりのため防災・防犯活動の充実
- 安定した町内活動を継続させるための人材登用と育成
- 町区民が愛着をもって住み続けられる魅力ある運営
- 自然環境・近隣環境の向上でより快適な暮らしを目指す
町区内のごみ減量・違反ごみゼロを
- 家庭ごみの分け方・出し方を確認して違反ごみをなくす
- 資源の日に出せるごみ出せないものを確認
- 違反ごみは燃やすための経費がかかる
- 資源の日に出すごみは町区の収入になる
- リデュース⇒ごみの量を少なくする
- リユース⇒いちど使ったものを何度も使う(びんなど)
- リサイクル⇒使ったものを資源に戻して製品にする
災害の時こそ「近助力」がものを言う
- 公助のきちんとした備えなしに町内会は立ち向かえない
- まずは「自助」「互近助」の防災隣組で命を護る
- 安否確認システムのインターネット避難訓練実施
- 避難場所の周知と整備
- 避難で効果的なのは近所の顔見知りによる声掛け